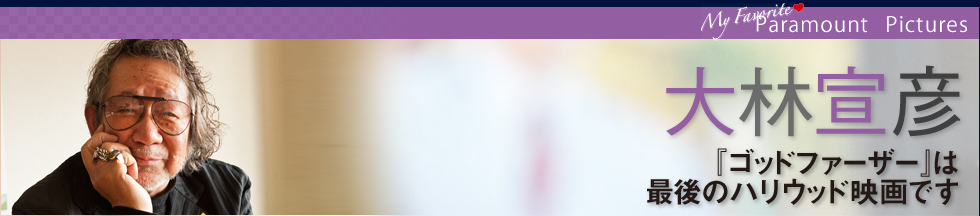


そして、キャスティング。それまでのハリウッド映画では「見慣れない顔」がたくさんあった。
「主演も当初はロバート・レッドフォードだったそうですね。原作(マリオ・プーゾが'69年に発表)も金髪なんだそうですよ。ハリウッドの理想のままにやったら、レッドフォードだったんでしょう。それがアル・パチーノだから。彼のように小柄な役者が主役をやるなんてことは、信じられないことであって。しかも猫背で(顔つきが)暗くて。美男子ではあるけど、いわゆるハンサムではないよね。当時は僕も思いましたよ、この人を3時間近くも観るのかい?って(笑)」
ジョン・カザールはもちろん、ジェームズ・カーンもロバート・デュバルもここまで大化けするとは思わなかったという。そして、当時、落ち目と言われていたマーロン・ブランドの圧倒的存在感。
「いま観ると、ブランドの出番って少ないでしょ。アタマちらっと、終わりちらっと。でも、全編支えてるんですよね。これはブランドの存在感というだけではなくて、ファミリーの映画だから、お父さんの存在がすべての人物に影を落としているんです。ジェームズ・カーンを見ても、アル・パチーノを見ても、ジョン・カザールを見ても、やっぱりそこにマーロン・ブランドを見てるんですよね。このへんが映画というものの、いわゆる感情移入させる面白さで。これが(コッポラが映画を)ファミリーでくくったことの大きな成功だっただろうと思うんです」
もうひとつ、重要な起用があった。それこそが『ゴッドファーザー』の独自性だったと大林監督は振り返る。
「落ち目のブランドに、あとは、まだスターでもなんでもない、チンピラばかりでしょ。なのに映画が風格を持ったのは、『大砂塵』('54)や『現金に身体を張れ』('55)のスターリング・ヘイドンが出ているからですよ。彼が警部役でちょっと出てきて、額の真ん中に穴を開けられて死んじゃうなんてシーンは、日本で言えば、『仁義なき戦い』の菅原文太さんが頭打ち抜かれて死んじゃう、みたいなこと。そういうシーンを撮っちゃった、っていうことが、この映画の凄さ。これはまさに“世代交代”という意図もあったでしょう。前の時代のスターを、息子の世代があんなふうに殺してしまうわけですから。またヘイドンの死に方もよかったんですよ。オレみたいなスターがこんな死に方しなきゃならんの?というようなスター自身の戸惑いもあそこにはある。こんな役、やるはずじゃなかったよ、オレの人生では、という。これがね、虚実の皮膜の面白さでね。僕がいちばん憶えているのは、あのシーンですね」
大林監督は、コッポラの編集技も同業者の観点から賞賛する。
「観客を飽きさせない。ロジャー・コーマン(膨大な数のB級映画群のプロデューサー/監督で、多くの監督、俳優が彼の許で映画を学び巣立っていった)学校の生徒であるコッポラには、その根っこがあるんです。だから、編集技術がすごく上手い。だから約3時間(177分)の映画が1時間半ぐらいにしか感じない。上映時間3時間なんて、当時のハリウッドではまずありえない。だから、2時間版もコッポラは作ったそうです。しかし、それを観たプロデューサーは“これは予告編かい? 全長版にしようよ”と言ったそうです。それだけテンポがよかった、ということですね。話芸にリズムがあるといけちゃう。『ゴッドファーザー』の編集には、ハリウッドの大作にあるような“ため”がない。ちょっとコミックなシーンがあると、お客さんは笑うでしょう? お客さんが笑い終わってから次のシーンにいくのが、それまでのハリウッドの基本の編集術だった。でも、僕なんかもそうだけど、観客が笑っている間に次のシーンにいく。もし次のシーンが怒りのシーンであっても、笑いと怒りが一緒になることで“劇”が生まれる。これがフィルムメーカーと言われた新しい世代の作劇なんです。コッポラの作劇も、ひとつのシークエンスが終わってないまま、その情感が次のシークエンスの情感と不協和音を起こす。コッポラの編集は不協和音を起こさせる編集。それが描かれたドラマだけではない、もっと深いドラマに拡げていく。複雑な感情のドラマを作ることにも成功しているし、同時に、観客はひと息つくヒマがないから、身を乗り出したまま、最後までいってしまう」

さらには脚本の巧みさ。
「コッポラは脚本も上手い。これはいまの若い監督にも学んでほしいんだけど、画コンテだけ描いて作った映画とはそこが違うんです。コッポラが、これだけ乱暴な作り方と、酷い条件のなかで成功したのは、やっぱりシナリオが書ける男だったということ。コッポラは時間軸の編集の上手さも含めて、映画全体を構成する――つまりコンポジションとメッセージをどう伝えるかということが、うまく出たんだと思います。『Ⅱ』はまさにそうでしょう? 過去と現在の不協和音。それが結果的にサーガになった。ハリウッド的なストーリーテリングのドラマツルギーを超えて、“感情”の映画になっているのは、確固たるシナリオのコンセプトと“ため”のない不協和音だらけの編集があったからですよ。雑然と混沌ですよ。整理整頓じゃなくて」
当時33歳の「若造」だったコッポラは、作家主義の映画作りを押し進めた結果、監督を降板させられる危機にも陥ったと言われている。
「コッポラは闘ってるんです、普通だったら諦めてしまうところを。新米のコッポラだったから、降りないで頑張った。最後まで粘って、自分の映画を撮った。プロデューサーたちはコッポラを降板させて、エリア・カザンに撮らせようとしていた。するとマーロン・ブランド(カザンの『波止場』でブランドはオスカーを奪取した)がそれを嫌がった。エリア・カザンの下では、また自分は言われる通りにやるしかない、コッポラとなら、好きなことができる、と。これが面白いところですよ。ブランドが“コッポラを降ろすなら、オレも降りる”と、強情を張って、それでコッポラを守った。でも、成功するって、そういうことなんですよ。映画って、いろんな条件が集まってできちゃうわけだけど、その条件が悪く働いて失敗するのではなく、稀にその条件がうまくいくってことがあるんですよね。その1本が『ゴッドファーザー』なんです。そういう意味では奇跡の映画。自分の自由にできない、でもやりたい。そのことがエネルギーになっている。アクションってね、画面に描かれたものだけじゃなくて、画面外の“アクション”が映画を活性化するんですよ。ロマンチックなファミリー映画のように見えるけど、画面外のアクションを、この映画はアクションにしているんです」
『ゴッドファーザー』は映画史において、ひとつの時代の終わりであり、新しい時代の始まりでもあった。
「僕らの世代にとっては、最後のハリウッド映画だけど、ここから映画を生み出していった人がいるわけです。端境期っていうのは、めちゃめちゃな混沌があるわけでね。混沌を捉える能力があると、何かが始まるんですよ。コッポラは、かつてのハリウッドが終わりゆくときに、リアリズムでもなく、夢でもなく、これは“私のマインドだ”というふうに撮った。だから成功したんですよ。それにしても、こんな映画は二度と作れないでしょうね。そういう意味でも映画的興奮がある名作です」
Text●相田冬二 Photo●利根川幸秀
(「パラマウント100周年記念厳選20作品DVD BOX(初回生産限定)」収録作品)